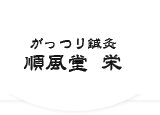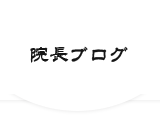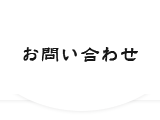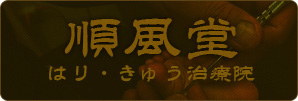健康診断の血液検査の項目と結果の正しい見方
健康診断の結果をもって当院に来られる患者さんもいます。
なんだかよくわからないですよね。患者さんと一緒に調べてこんな記事を見つけました。
血液検査の必要性、検査でわかることとは?
血液検査とは、血液中のさまざまな数値を調べることで、そこから考えられる病気や、数値の裏に隠れている疾患などを見つけるための検査です。体の中を巡っている血液を確認して分析することで、健康状態を知り、何らかの異常が起きた時に、それを発見することも可能です。
血液検査で調べられる数値からわかるのは、貧血や肝臓・腎臓の異常、高脂血症、糖尿病など。血液検査からわかることはとても多く、健康を知るためには有効な検査と言えます。
血液検査の数値の見方を知りましょう
肝臓系検査
●総タンパク:血液中に含まれるタンパクの量
数値が低い場合…栄養障害/がんなどの疑い
数値が高い場合…多発性骨髄腫/慢性炎症などの疑い
●アルブミン:血液タンパクのうちで最も多く含まれるもの
数値が高い場合…肝臓障害/栄養不足/ネフローゼ症候群などの疑い
●AST(GOT):心臓、筋肉、肝臓に多く存在する酵素
数値が高い場合…肝臓障害、骨格筋疾患、血液疾患などの疑い
●ALT(GPT):肝臓に多く存在する酵素
数値が高い場合…急性肝炎/慢性肝炎/肝臓がん/アルコール性肝炎などの疑い
●γ-GTP:肝臓や胆道に異常があると、γ-GTP値が上昇
数値が高い場合…アルコール性肝障害/慢性肝炎/薬剤性肝障害などの疑い
腎臓系検査
●クレアチニン(Cr):アミノ酸の一種「クレアチン」が代謝された後の老廃物
数値が高い場合…腎臓の機能が低下気味
尿酸(UA)
●尿酸:たんぱく質の一種「プリン体」が代謝された後の残りかす
数値が高い場合…高尿酸血症の疑い。また、高い状態が続くと結晶として関節に蓄積し、突然関節痛・痛風発作を起こす場合も。尿路結石が作られやすくなる
脂質系検査
●総コレステロール(TC):血液中の脂質
数値が高い場合…動脈硬化/脂質代謝異常/甲状腺機能低下症などの疑い
数値が低い場合…栄養吸収障害/低βリポたんぱく血症などの疑い
●HDLコレステロール:善玉コレステロール
数値が低い場合…脂質代謝異常/動脈硬化の疑い
●LDLコレステロール:悪玉コレステロール
数値が高い場合…血管壁に蓄積し、動脈硬化を進行。心筋梗塞/脳梗塞の危険
●中性脂肪(TG)(トリグリセリド):体内の中でもっとも多い脂肪
数値が高い場合…動脈硬化の進行の疑い
数値が低い場合…低βリポたんぱく血症/低栄養などの疑い
糖代謝系検査
●血糖値(FPG):血液中のブドウ糖
数値が高い場合…糖尿病/膵臓癌/ホルモン異常などの疑い
血球系検査
●赤血球:酸素を全身に運び、不要となった二酸化炭素を回収して肺へ送る
数値が高ぎる場合…多血症の疑い
数値が低すぎる場合…貧血の疑い
●白血球(WBC):細菌などから体を守る働きがある
数値が高すぎる場合…細菌感染症などの疑い(発生している部位は不明)
数値が低すぎる場合…ウィルス感染症/薬物アレルギーなどの疑い
●血小板数(PLT)…出血時に粘着し、血を止める働きがある
数値が高い場合…血小板血症/鉄欠乏性貧血などの疑い
数値が低い場合…再生不良性貧血などによって、骨髄での血小板数の生産が低下しているなど
う~ん やっぱりわかりにくいですよね。話しやすい、聞きやすいお医者さんを見つけるのが良いですね。