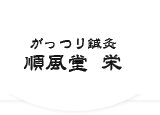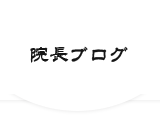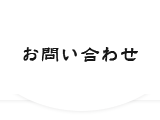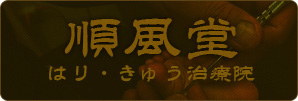「秋の花粉症」を自覚したら、草むらと果物には注意すべき理由
風邪なのか?コロナなのか?心配でしょうがない患者さんとの会話で見つけた記事です。
「秋の花粉症」を自覚したら、草むらと果物には注意すべき理由
日に日に秋も深まり、急激な温度変化で体調を崩す人も増えてきた。くしゃみや鼻みずが出ると、最初に疑うのは風邪だが、今年に限っては新型コロナ感染症もあるので、厄介だ。もう一つ、「秋の花粉症」の可能性があることも忘れないようにしたい。
● 花粉症には9~10月がピークの 「秋バーション」がある
「今年の春は、咳やくしゃみをするたび周囲から引かれてつらかった」という花粉症患者は、多いのではないだろうか。そう、新型コロナウイルスによる感染症は、風邪、花粉症に症状が似ている。ゆえに、周囲はもちろん本人も、喉の痛みや咳、痰、鼻汁や鼻詰まり、発熱、倦怠感などがあるとつい、「もしや、新型コロナ?」とビクビクせずにはいられなかったのだ。
しかも、過酷な現実は秋にも待ち受けていた。花粉症には秋バージョンがあるのだ。春先の花粉症が主にスギやヒノキ、カバノキ科の花粉によるものであるのに対し、秋の花粉症はイネ科の草やブタクサ、ヨモギ、カナムグラの花粉によって起きる。
イネ科といっても、主に問題となるのは田んぼの稲ではない。花粉症の原因となるイネ科の植物はたくさんあり、気候や地域差がある。春の花粉症が収束するのと入れ替わりで飛散し始めるカモガヤとハルガヤは4~7月、ギョウギシバは6~8月、オオアワガエリは5~8月、アシやススキは8月~9月に花粉が多く飛散する。穂先を風に揺らす姿は確かに、イネに似ている。
ただ秋の花粉症の主役はブタクサ、ヨモギだ。日本全国いたるところで見かけるありふれた植物で、9~10月に飛散のピークを迎える。
ブタクサはキク科の一年草で、北アメリカ原産の外来種。同じく外来種のセイタカアワダチソウによく似た黄色くて小さな花を大量につける。日本では花粉症といえばスギ、ヒノキ花粉症が圧倒的だが、原産地である北米大陸では花粉症といえばブタクサがメインで全人口の5~15%がブタクサ花粉症との統計があるという。
一方のヨモギはキク科の多年草で、日本全国に自生している。清らかな香りがあり、春の地表に生える若芽は草餅にも使われる。お灸のもぐさや漢方の原料にもなるほど利用価値が高い、愛すべき植物なのだが、初秋になると地味な花をつけ、風媒花のため多量の花粉を飛ばす。花粉症がある人にとってはやっかいな植物なのである。
ネットではよく、カナムグラも紹介されている。アサ科(以前はクワ科)カラハナソウ属つる性の1年草で、万葉集でも詠まれているほど昔から生息している。長くつるを伸ばし周囲に縦横無尽に絡みつくため、除去するのはかなり困難で、一度発生すると辺り一面を覆ってしまうほど繁殖力が強い。つる状の茎には鋭いトゲがあるので腕や脚で直接擦ると刺さって痛い目にあう。ただし、患者の数はあまり多くはない。
● 土手のランニングに注意 アナフィラキシーの危険も!
日に日に秋が深まる時期は気温の変化が大きく、空気も乾燥してくるため風邪を引きやすい。くしゃみや鼻みずが出ると、最初に疑うのは風邪だが、秋の花粉症の可能性があることも忘れないようにしたい。スギ・ヒノキよりも粒子が小さいブタクサの花粉症では、気管支に花粉が入り込んで喘息のような症状が出ることもある。そのためブタクサは別名「喘息草」と呼ばれているほどだ。むろん、新型コロナも心配だ。熱もないのに咳が続くときは自己判断せず、病院を受診しよう。
また、心地よい秋風が吹いてくると、運動やバーベキューなどで川沿いの土手や雑草の群生地に足を踏み入れる機会も増えるが気を付けたい。草むらで大量の花粉を吸収すると、じんましんや呼吸困難などの強いアレルギー反応を起こすアナフィラキシーショックをきたすことがある。
今年の春は花粉の飛散量が例年の半分程度だったことに加え、コロナ禍のせいで外出を控えたり、常時マスクをつけて過ごす人が多かったため、「いつもの年より花粉症のコントロールが上手くいった」という人は多い。
秋の花粉症対策も春同様、基本はできるだけ花粉を浴びないようにすることに尽きる。幸い、これらの植物はスギやヒノキのような樹木と違って背が低く、飛距離はせいぜい数百メートルで、遠くまで飛散することはない。何となく花粉症っぽいと感じたら、雑草が群生しているような場所には近づかないようにするのが一番だ。
● 花粉症の患者がなりやすい 花粉食物アレルギー症候群
さらに、秋の花粉症の患者は、果物や野菜などを食べたときに口の中や唇にイガイガしたかゆみや痛みを感じる・顔面が腫れる・呼吸がしづらく感じるなどの症状が表れるOASと呼ばれる口腔アレルギー症候群を起こしやすい。これは「交差反応」といって、アレルギーの原因となる花粉に含まれるたんぱく質の一部と、果物や野菜などに含まれるたんぱく質の構造が似ているために起きる。交差反応を起こしやすい果物や野菜は、花粉の種類ごとに異なる。イネ科やブタクサ、ヨモギなどの花粉は、ウリ科(メロン、キュウリ、スイカ)、オレンジ、トマト、バナナ、アボカドなどとの組み合わせでアレルギーがでやすい。このように口腔アレルギーが花粉と関連してあらわれる場合、花粉食物アレルギー症候群と呼ばれる。
またこのアレルギーの原因となるたんぱく質(プロフィリン)は熱や消化酵素に弱いため、反応は主に口腔内だけで起きると言われているが、「実際には口腔咽頭症状のみならず呼吸困難、アナフィラキシーなどの全身性アレルギー症状をきたす症例も決して稀ではないので注意が必要である」食物アレルギーのQ&A』で述べている。
なんとも恐ろしい、どうしたらいいのだろう。
「理由は明確になっていないが、プロフィリンにアレルギーをきたす患者は最初に、メロンなどのウリ科に反応して、その後徐々に反応する食物が増えることが多い」とも述べている。ということは、メロンなどのウリ科の食物でアレルギー症状がある人は、秋の花粉症に関連した食物アレルギーになっている可能性を疑ったほうが良いかもしれない。
それでもし、食物アレルギーの兆候があった場合、対策としては、特に花粉飛散時期に原因食物を摂取すると重篤な症状をきたしやすいので、9~10月にかけてはこれらの食物を食べないようにするか、プロフィリンは加熱で抗原性を失いやすい性質があるので、加熱してから食べるようにするというのはどうだろう。
ただし、素人判断はやはり禁物。アレルギーかもと思ったら、早いうちに専門医を受診することをお勧めする。アレルギー専門医、指導医がいる医療機関は、『日本アレルギー学会』のウェブサイトで検索しよう。
風邪なのかアレルギーなのか見極めは難しいです。
普段から自分自身の健康に目を向けることで自身の変化に気づき受診しましょう。