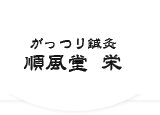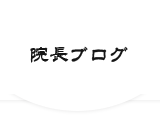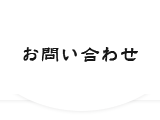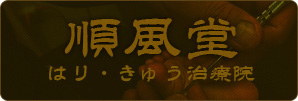夏を乗り切る水分補給のポイント
カテゴリー:院長スケジュール2015年08月17日(月)
ジワジワと気温が上昇する日が続きます。気を付けなければならないのが「熱中症」です。そのために不可欠なのが水分補給。では、何に注意して水分補給をしたら良いか考えてみましょう。
水分不足、どんな影響があるの?
・血液ドロドロ 疲労の要因にも
気温が高くなれば多量の汗をかき、多量の水分を体外に放出します。体内の水分が不足すると、血液中の水分がなくなり、血液がドロドロの状態になり、老廃物や栄養成分の運搬が滞る。そうなると疲労を招くだけでなく、放っておけば突然死の原因にもつながってしまいます。
・多量の水を飲まなくても大丈夫
一般的に、食事などで体内に取り入れる水分と、体外に放出される水分はイコールにしたほうがいいと言われ、目安は2.5リットルとされています。とはいえ、前述のように発汗量の増える夏場は排出される水分が増えるので、食事や飲料でより多くの水分を摂取しなければなりません。そう言われると、とにかく水をたくさん飲まなきゃ、と考える人もいると思いますが、呼吸に含まれる水分、野菜など食材に含まれる水分もあるので、食事にプラスして水分摂取を多めにする、という意識で十分です。
・“水だけ摂取”は脱水症状の原因にも
また、水だけを摂取していたら体液の濃度も急速に薄まってしまいます。そうなると体はどんな反応を示すのか。薄まった分の濃度を調節しようと、本当は必要な水分を「余分」と判断し、体外へ排出しようとするので、自発的脱水と言われる症状が発生し、汗をかくだけでなくトイレへ行く回数も増えてしまう。水を飲んでいるにも関わらず、脱水症状が起きてしまうのです。
・水分に加えて「ミネラル補給」を
夏場は汗で水分が失われるだけでなく、同時にミネラルも排出されます。ミネラルは筋肉の収縮や振動の拍動に関係するので、体内のミネラルが不足すると細胞内液、細胞外液の浸透圧のバランスが崩れてしまい、普段以上にだるさを感じるようになります。
では実際に何をどんなタイミングでどれぐらい飲めばいいのでしょうか。
汗をかいたら、何を飲んだらいい?
・「硬水のミネラルウォーター」……汗が少ない人におすすめ
こうした状況を招かないためにも、スポーツで多量の汗をかく人は特に、水分だけでなく失われたミネラルも一緒に摂取しなければなりません。
水分とミネラルを同時に補給するために、よく用いられるのはスポーツドリンクです。スポーツドリンクには糖分も含まれているので、運動に必要なエネルギーも摂取することができるのでとてもありがたいものですが、人によって発汗量は違うので、スポーツドリンクに含まれるほどのミネラルを必要としない人もいます。「自分はあまり汗をかかない」と感じる人は、軟水ではなく硬水のミネラルウォーターを選ぶだけでもいい。お茶や軟水を飲むという人は、まず硬水に変えてみたらいかがでしょうか。
最近ブームの炭酸水も硬水が多く含まれたものがあります。人工的につくられた炭酸水ではなく、ペリエなど海外で自然発生したガスウォーター、炭酸水は硬水なのでミネラルも豊富。食事の前にたくさん飲みすぎてしまうと胃が膨らんで食事ができなくなってしまいますが、数口ならば炭酸水には食欲増進効果があるので、夏バテ気味だという人は炭酸水を少し飲んでから食事をすると、胃の分泌をよくすると言われています。
・「牛乳」「飲むヨーグルト」……タンパク質+糖質で疲労回復
多量の発汗でミネラルが放出された時に塩分を欲するように、疲れている時に「エネルギーを摂取したい」とジュースや炭酸飲料など甘みのある飲み物を欲する人も少なくないのではないでしょうか。
運動することで下がった血糖値を上げるために甘いものを摂取すればいい、と考えるかもしれませんが、疲労を早く回復することを考えると、糖質だけでなく一緒にタンパク質を摂取したほうがいい。運動後はジュースよりも牛乳や飲むヨーグルトを選んだほうが疲労回復には効果があるはずです。
・「果汁100%ジュース」……紫外線で失ったビタミンCを補給
梅雨が明けると太陽の日差しも強くなり、紫外線値も高くなる。そうなればビタミンCが失われるので100%のオレンジジュースやグレープフルーツジュース、トマトジュースなどビタミンCを豊富に含む飲み物を選ぶようにするとダメージは減少します。飲むだけでなく、野菜は水分が豊富なので食事の時にサラダを食べるようにする、というのも効果的です。
夏の水分補給 意外な事実
・果物風味の“水” 中身はほぼジュース
ただし気をつけてほしいのが、最近多く売られているレモンやオレンジ風味の水。パッケージが水と同じものが多いので、「これも水だ」と勘違いしてしまうかもしれませんが、ボトルのパッケージが水に似ているだけで、中身は糖分の多いジュースと同じ。成分表をよく見ると、炭酸飲料や果汁の少ないジュースとさほど変わらないのが分かるはず。
・冬より低い夏の基礎代謝 過剰な糖分に気をつけて
汗をかくので「夏場は少しぐらい糖分を摂取しても太らない」と思うかもしれませんが、実は基礎代謝は冬よりも夏のほうが低い。つまり夏の方が太りやすいのです。水分しか飲んでいないはずなのに、糖分の多い飲み物ばかり飲んでいて太ってしまった、ということも珍しいことではありません。
飲み物に最適な「温度」って?
糖分を取り過ぎないという面でも意識するといいのが水分と温度の関係です。同じ飲み物でも、冷たいものよりも、ぬるく感じるもののほうがより甘味を感じませんか? 飲み物の温度は5〜15度が体内へ吸収するのに一番適していると言われています。夏場、暑い時期には冷たいものをたくさん飲みたくなりますが、「ちょっとぬるいな」と感じるものの方が、体内への吸収もスムーズですし、甘味を感じられるので過剰な糖分摂取の防止にはおすすめです。暑いからと言って冷たいものばかりを飲み過ぎないようにしましょう。
どうでしょう?たかが水分、されど水分ですね。奥が深いと思います。水分の取り方ひとつでも効率的に効果的に摂取しようとすれば様々なやり方があります。医学的に良いと言うものの実践は難しいものです。でも東洋医学的には昔からの風習や習慣の中に良い方法が盛り込まれているときが多いんです。
暑いときのスイカに塩をかけて食べるのは美味しくなるし、水分もミネラルも、塩分も取れますよね。美味しく暑い夏を乗り切りましょう。