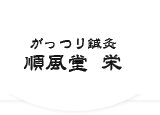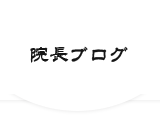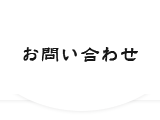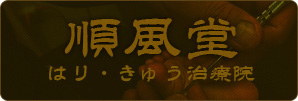肩こりに悩むママに朗報♪「ピップエレキバンfor mama」で”ママこり”を改善!
カテゴリー:院長スケジュール2019年02月21日(木)
今も昔もママは大変ですよね。順風堂は新米ママさんからベテランママさんまで多くのママさんが来院されます。ママさんにオススメグッズを見つけた記事です。
肩こりに悩むママに朗報♪「ピップエレキバンfor mama」で”ママこり”を改善!
妊娠中は重いお腹に悩まされ、「出産してようやく身軽になれた♪」なんて思っていたら大間違い。じつは今、首や肩、腰のコリを訴える産後ママが増えています。実際に、ある調査では産後ママの約8割が「コリ症状を悪化させた」というデータが出ています。 そんなママのために生まれたのが、「ピップエレキバン for mama」♡ 磁気治療器で知られるピップが、子育てに奮闘するママのために開発した、肩こり改善の心強いアイテムです。
産後ママに赤信号!子育て中のツライ肩こり
子育て中のツライ肩こり
育児による“ママこり”で、とくにツライのが肩こり!
可愛い我が子だけじゃなく、重い荷物や育児ストレスなど、ママの両肩には大きな負担がずっしりとのしかかってきます。
とくに最近の育児事情が、ママへの負担を増大させています。
重い荷物と大型化するベビーカー
実際に子育てを経験して驚くのが、荷物の量と重さです。
オムツにおしり拭き、消毒シートに哺乳瓶、授乳ケープにおくるみなど、ママのバッグにはたくさんの育児グッズが入っています。
また最近のベビーカーは安定性や操作性を重視する傾向が強く、ベビーカーの大型化が進んでいます。
赤ちゃんを前で抱っこするおしゃれな抱っこ紐も、今では一般的になりましたよね☆
一見、便利に思えるこれらの育児グッズも、じつは肩に負担をかける原因となっているんです。
子どもとのお出かけも一苦労
子どもとのお出かけ、とっても楽しいですよね♪
でも、「電車やバスで泣かれたら…」「周りの人に迷惑をかけたら…」と、外出先にはママのストレスの種がたくさん落ちています。
ストレスは自律神経を乱し、血行を滞らせる原因となってしまいます。ママの肩こりには、ストレスが引き起こす血行不良によるものも多いのです!
授乳や抱っこも要注意
授乳や抱っこといえば、ママと子どものふれあいタイム♡
親子で過ごす、とっても幸せなひとときです。
しかし、授乳や抱っこをしているとき、ママは無理な姿勢をとっていることが少なくありません。たとえ無理な姿勢ではなくても、長い時間、同じ姿勢でいるのはツライもの。
抱っこや寝かしつけといった親子のふれあいタイムにも、肩こりの原因は隠れています。
セルフケアで肩こり改善♪
子育て中のツライ肩こり
忙しいママのため、ここでは短時間でできる肩こりの改善方法をご紹介します♡
まずは正しい呼吸法により、自律神経を整えましょう。
背筋を伸ばしたまま、鼻から息を吸って口からゆっくり吐き出します。
たったこれだけで、ゆったりと落ち着いた気分になるはずです。
いつでも気がついた時に、5回ほど繰り返しましょう。
次に、入浴による血行促進をオススメします。
少なくとも週に一度は湯船にお湯を張り、肩までしっかり浸かりましょう。
40℃以下のお湯に、10〜15分ほどゆっくり浸かるのがポイントです。
また、簡単な体操も肩こりの改善には効果的です。
固まった筋肉を動かすように、ゆっくりと伸ばしていきましょう。
首・肩周りの筋肉を動かすには、右手を左側頭部にあてて首をゆっくり右下に倒していきます。
このとき左手は左下方向に一直線に伸ばしておきます。
左の首筋から肩にかけて、筋肉が伸びていることを意識してください。
右側も同様に行います。
ついに発売!ママのための「ピップエレキバン for mama 」
ピップエレキバン for mama
<商品>
ピップピップエレキバン for mama /オープン価格
前述のセルフケアと並行して使っていただきたいのが、「ピップエレキバン for mama 」♪
ピップエレキバンやピップマグネループなど、大ヒットの磁気治療器を世に送り出してきたピップが、子育てママのために開発した新商品です。
もともと磁気治療器は薬剤を使わず安心で、子育て中のママにはピッタリ♡
貼っている間、磁気の力で血行を促進し、コリをほぐしてくれるのも魅力的です。
そんな磁気治療器に、ママならではの使いやすさを加えたのが「ピップエレキバン for mama 」。
同商品では磁石の色を従来の黒からベージュに変更し、絆創膏から透けにくいようになっています。
子どもって、珍しいものがあると絶対に手を伸ばしてきますよね。
そのため絆創膏も磁石も肌になじむベージュで、子どもには気づかれにくい見た目となっています。
また匂いがないため、子どもが肩に頭を預けてきても大丈夫。
伸縮性や透湿性に優れ、ママ自身の肌に優しいのも嬉しいですね☆
さらに乳幼児が開けにくいよう開け口を底部に作るなど、パッケージにもひと工夫が見られます。
ピップが「ママこり改善委員会」まで立ちあげて、ママのために開発した新商品。
ママを肩こりから解放してくれる、頼もしいアイテムです☆
産後ママの肩こり改善法と「ピップエレキバン for mama 」、いかがでしたか?
育児の基本は、ママの健康です♪「自分をケアする時間はない」なんて言わずに、ぜひママの肩こりもケアしてくださいね。
ママさん大変ですよね。ママさんじゃなくても大変ですからね。
鍼灸も同じ様に妊婦、ママさんなど薬を使うことができない方に効果的な治療方法です。気分転換に鍼灸治療いかがですか?
当院では赤ちゃんを一緒に連れて来ていただいても大丈夫です。