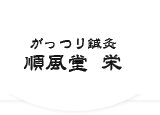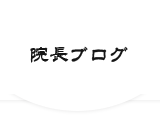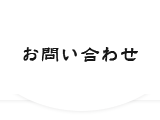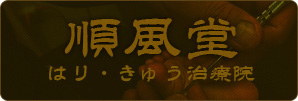肩こりや目の疲れに最適!エコな小豆カイロで身体を温めよう♪
カテゴリー:院長スケジュール2020年02月28日(金)
冬とは思えない温かさ でも最近足が冷えると感じる人が多いです。
そんな会話の中で見つけた記事です。
肩こりや目の疲れに最適!エコな小豆カイロで身体を温めよう♪
乾燥の時期気になるドライアイや寒さから起きる肩こりや目の疲れなど、冬は身体に様々な不調が出やすくなります。使い捨てカイロなどで温める方法もありますが、最近では何度も繰り返して使えるエコな小豆カイロが人気を集めています。
冬の時期に起きる体の不調
毎年冬になると身体に不調が現れる人は、もしかすると「冷え」と「乾燥」が関係している可能性があります。特に肩こりや目の疲れ、ドライアイなどが冬に酷くなる人は該当しているかもしれません。
寒い時期は、手足だけでなく首や肩も血流が低下し肩がこりやすくなります。しかも肩がこると血行不良になりやすく、身体も冷えるという悪循環に。
また、乾燥する時期は目を保護する水分量が減ってしまうので、ドライアイによる眼精疲労が辛くなるケースもあるのです。
小豆が身体を芯から温める理由
暖房やカイロで身体を温める方法もありますが、暖房は室内の水分を奪って乾燥を加速させます。またカイロは乾燥物で乾いた熱の為、浸透率が悪く身体の芯まで温めるのは難しいと言われています。
そこで今注目を集めているのが“小豆を温めて作るカイロ”です。小豆には豊富な水分が含まれていて温めると自然に水分が蒸気となって出て来ます。お風呂に入ると身体の芯から温まるように、湿熱は身体をしっかりと温めて保湿をしてくれるので、目に使えばドライアイや長時間のパソコン使用による眼精疲労も緩和されます。
小豆カイロの作り方
小豆カイロの作り方はとっても簡単で、しかも一度小豆から出た水分は時間経過とともに自然と戻ってくる性質があり、何度も繰り返し使えるのでエコにも繋がります。
小豆カイロの作り方
(1)綿100パーセントの巾着を用意します。
(2)小豆をお好みの量、溢れない程度に詰めてしっかりと紐で口を結びます。
(3)電子レンジで30秒~60秒ほど温めて出来上がりです。
小豆の他にも玄米や米ぬかなどもカイロ代わりとして使用ができるので、自分の好みの素材を試してみてくださいね。
ただし注意点…!
小豆は長時間加熱をすると爆発する場合があるので60秒以上は加熱してはいけません。また、一度小豆から抜けた水分は4時間ほどかけて戻ってくるので、再加熱には時間を空ける必要があります。
カイロに使用する布は化学繊維の物を使用すると加熱した際溶けてしまう可能性があるので必ず天然繊維100パーセントの物を使用するよう、注意してください。直接肌につけて使用するのも火傷の原因に繋がるので注意が必要です。
ただ、小豆カイロは、200回ほど使ううちに効果が薄れてくるので「温まるのにいつもより時間がかかるようになった」と思ったら、中の小豆の変え時です。
蒸気と遠赤外線効果によって身体を芯から温めてくれる小豆カイロは自分でも簡単に作れる上、何度も繰り返し使えるのでとてもエコな温活グッズです。オフィスでのちょとしたリフレッシュにもおすすめです
世間は新型コロナウイルスで大騒ぎです。ストレスは免疫力を下げてしまいます。
ちょっとリラックスることも感染予防になります。
スマホの見過ぎで頭痛!?今すぐできるストレートネック対策
カテゴリー:院長スケジュール2020年02月20日(木)
首や腰の痛みを訴える人が多いです。そんな時に見つけた記事です。スマホの見過ぎで頭痛!?今すぐできるストレートネック対策
「頚椎(けいつい)」とよばれる首の骨は、頭を支える働きをしています。通常、頚椎はまっすぐな状態から30~40度反っています。頚椎が何らかの原因でカーブが不足した状態を、「ストレートネック」と呼びます。首には多くの神経が通っており、首の不調は全身の不調につながるため、早めにストレートネック対策をしていきましょう。
自分でできる簡単なストレートネック対策方法をご紹介します。
■「ストレートネック」になる要因・症状のチェックリスト
ストレートネックになる要因は、下記のような行動・状態です。あてはまる項目が多いほど、ストレートネックになる危険性が高いといえます。
□パソコンを長時間使い、同じ姿勢でいることが多い
□スマートフォン・タブレットを長時間見つづける
□高いヒールをよく履く
□外反母趾がある
□扁平足である
□楽器を演奏する
□激しいスポーツをよくする
□骨盤のバランスが歪んでいるといわれたことがある
骨盤のバランスの乱れや足の不調が、ストレートネックにつながることもあります。
ストレートネックによる症状
・吐き気
・めまい
・頭痛
・首が回らない
・上を向きにくい
・気分が落ち込む
・やる気が出ない
身体の症状だけではなく、心の症状(うつ状態など)もあらわれることがあります。また、最近では自覚症状がないけれどストレートネックという人も増えているようです。
不調がおさまらず、痛みが続く場合は、正しい診断を受けるためにも早めに整形外科を受診しましょう。
■簡単!自分でできるストレートネック対策法
タオルストレッチ
タオルさえあれば、どこでもできるストレッチ法です。
(1)タオルの両端を持ち、首にかけるようにあてます。
(2)そのまま斜め上に両手を上げて、首を後ろに軽く倒しながら、タオルを斜め上に引っぱります。そしてそのままゆっくりとあごを引き、下を向きます。
この動きを1日に5セット行いましょう。
テニスボールを使ったストレッチ
自宅でテレビを見ながら、あるいは寝る前などにできる方法です。
(1)テニスボール2個をガムテープなどで巻いて、離れないよう固定します。
(2)床に仰向けになって、くっつけたテニスボール2個を首の後ろ、頭と首の境目の関節にあてて、リラックスして1〜3分その状態を保ちます。
これで、ストレートネックを予防できます。
寝具(主に枕)の見直し
実は、枕の高さが合っていない場合もストレートネックになる危険性が高まります。枕だけではなく、「敷布団がかたすぎる、やわらかすぎる」という場合も同様です。
オーダーメイド枕で自分に合った枕や寝具を選ぶのも、一つの対策になります。
ただし、高価なものが良いわけでも、安いものが悪いというわけでもありません。自分に合うものを見つけるため、何個か試してみることがおすすめです。
最近では首を酷使していることに気がつかず、ストレートネックになる人も多いようです。日々のストレッチや寝具の見直をするだけでもストレートネック対策になります。
不調の原因となるストレートネックを改善・予防するために、入浴中や仕事の休憩時間など、気がついた時にストレッチをしてみてはいかがでしょうか。
いろいろな対処法の一つと考えていただけると助かります。
僕は如何に力を抜くか?がポイントだと思っています。
鍼灸治療は肩の力を抜くことができます。ストレートネックにも効果ありですね。
しんきゅう通信2月号
カテゴリー:院長スケジュール2020年02月05日(水)

最近、寒い日が出てきましたね。
しんきゅう通信2月号です。
そのつらい頭痛、月経前から月経中にかけて症状が出ていませんか?
カテゴリー:院長スケジュール2020年01月31日(金)
そのつらい頭痛、月経前から月経中にかけて症状が出ていませんか?
片頭痛にはエストロゲンの急激な現象が関係
頭痛でやる気がなくなっている女性
片頭痛に女性が多い理由として、女性ホルモンとの関わりが挙げられます。
「女性ホルモンには、主にプロゲステロンとエストロゲンがありますが、エストロゲンの急激な減少が片頭痛の誘発因子になると考えられています。月経周期の中で、エストロゲンが減少するのは、月経前から月経中にかけて。そのため、この時期に片頭痛が最も起こりやすくなります。月経前緊張症(PMS)のひとつと思われがちですが、この時期に頭痛を感じる人の約80%は、片頭痛と考えられます。
やっかいなことに、月経に関連した片頭痛は、ほかの誘発因子で起こる片頭痛に比べて痛みが強く、持続期間も長くなる傾向があります。市販の鎮痛薬を飲んでも効果がなかったり、その日はよくなっても、翌日にぶり返すことがあります」
毎月、決まって起こる片頭痛に、この時期を恐れて、不安な気持ちで日々を過ごすなど、生活に支障をきたす人も。月経前緊張症だから仕方がないと、あきらめている人も多いようです。
「不安感やネガティブな気持ちでいると一般的に痛みは悪化しやすいもの。セルフケアや病院での治療で、頭痛を軽くすることもできます。頭痛への対処法を知って、ラクな気持ちで生活することも大切です」
妊娠中や更年期を過ぎると片頭痛が軽くなる
一方で、閉経後は、女性ホルモンの変動が少なくなるため、3人に2人は片頭痛がよくなるといいます。
「ただ、閉経前後の更年期は、女性ホルモンが不規則に変動することで、片頭痛がひどくなることも。また、エストロゲンの変動以外の誘発因子でも片頭痛は起こります。更年期は夫の定年や子どもの独立、会社で責任ある立場になるなど、家庭的にも社会的にも変化が多い時期。ストレスや生活パターンが変わることに加え、ホットフラッシュやめまい、肩こりといった更年期症状が現れることで、片頭痛が重症化することもあり、注意が必要です」
また、妊娠中は、エストロゲンが高レベルで維持されるため、片頭痛持ちの妊婦さんの6~8割は、妊娠6か月以降は片頭痛がなくなるそうです。しかし、出産後1か月以内に半数の人は片頭痛が再発するという報告もあります。授乳中でも服用できる薬はあるので、頭痛外来などに相談しましょう。
疲労回復の権威が教える「疲れ」のとり方。ほぐすべきは肩より脳!
カテゴリー:院長スケジュール2020年01月24日(金)
疲れが全く取れないという患者さんとの会話で見つけた記事です。
疲労回復の権威が教える「疲れ」のとり方。ほぐすべきは肩より脳!
マッサージに行っても、お風呂にゆっくりつかっても、スッキリ疲れがとれない……。
何だかいつも、体が疲れている。そこには、意外な理由があるようです。疲れがとれない本当の原因だけではなく、根本的な対処法が紹介されています。
疲れの原因は「脳」にある
「何をやっても疲れがとれない」人は大勢います。しかし、肩こりや腰のこわばりがあるから、肩や腰に問題があるとは限らない。筋肉そのものに原因があるわけではない。
脳が疲れると、自律神経が乱れがちになります。すると、体に気になる症状が出てきます。体の症状に対処しても、大元の脳に対処しなければ根本的な解決にはなりません。
『疲労回復の名医が教える 誰でも簡単に疲れをスッキリとる方法』3ページより引用
実は、疲れているのは筋肉ではなく、「脳」にあると著者はいうのです。
脳には自律神経のコントロールセンターがあり、24間365日稼働しています。そこに過度な負担がかかったとしたら、脳が疲れてしまうということは当然でしょう。体の症状だけではなく、脳の疲れをスッキリとることが、全身の疲れにアプローチしていくことにつながるようです。
「疲労」と「疲労感」は必ずしも一致しない
逆に、楽しいことややりがいがあることをしていると、あまり体の疲れを感じないことがあります。それは、なぜなのでしょうか。
疲労とは何かを科学的に理解するとき、もうひとつ重要な知見があります。それは、「疲労」と「疲労感」とが必ずしも一致しないという事実です。
『疲労回復の名医が教える 誰でも簡単に疲れをスッキリとる方法』24ページより引用
疲労を起こすのは、おもに脳内にある自律神経の中枢で、視床下部、辺縁系、全帯状回などといった回路。つまり、脳の中心部分です。
反面、疲労したという情報を集めて疲労感を感じさせるのは、大脳の前頭葉にある眼窩前頭野(がんかぜんとうや)という部位。つまり、疲労が起きる部位と、疲労を自覚する部位がそれぞれ違っているのです。
飽きだしたら、脳が疲れているサイン
だとしたら、脳が疲れているときに表れるサインを、どのように正しく見極めたら良いのでしょうか。
脳が疲れていると、「飽きる」「作業効率が落ちる」「眠くなる」という3つのサインが現れます。
『疲労回復の名医が教える 誰でも簡単に疲れをスッキリとる方法』28ページより引用
脳疲労の3大サインとして、「飽きる」「作業効率が落ちる」「眠くなる」が挙げられています
最初に現れるサインは「飽きる」。作業を続けていると、脳内で同じ神経細胞の回路が使われます。そのため、活性酸素が発生して、神経細胞が酸化してしまいます。酸化が進むと、修復が困難になり、脳が「違う神経細胞を使え」と、指示を出すため、飽きてしまうのです。サインを感じたら、休息をとって、脳をしっかり休めることが重要です。無視したまま続けていると、自律神経が疲れている状態が続き、高血圧症や糖尿病、がんの発症リスクが高まってしまうというのです
自分が感じる疲労感だけに頼らず、3大サインが出たらちょっと休む。脳の疲れを蓄積させないためのコツであるといえそうです。
「睡眠」と「こまめなリセット」で脳の疲れをとる
それにしても、気をつけていてもたまってしまう疲れは、一体どう解消したらいいのでしょうか。
脳を休めて回復させるには、毎日の疲れをリセットすること。その最適な方法はよい睡眠をとることです。
『疲労回復の名医が教える 誰でも簡単に疲れをスッキリとる方法』36ページより引用
脳の疲れを取るためには、やはり睡眠をとること。しかも、質のいい睡眠で、自律神経の疲れをとっていくことが大事なようです。
よい睡眠を得るためには、安全で快適な環境がポイントになると著者はいいます。
たとえば、就寝1時間前になったら、できるだけテレビやパソコンから離れて、刺激の強い光を避ける。そして、就寝3時間前には、部屋の照明をオレンジ色に変えることを勧めています。
暗くなって眠くなるのは、脳内でメラトニン(睡眠ホルモン)が影響するからであることは有名です。そのメラトニンは、朝起きたときに生成されるセロトニンが、起床後14~16時間たって姿を変えたものです。
メラトニンの分泌を正常化するためには、眠りに入る前の3時間、昼の光に近い明るい光を浴びないことが理想だといいます。自然界における、夕方から夜に変わっていく環境を再現することで、睡眠モードへの準備が整っていくといえるでしょう。
そして、目を瞑るだけでも脳をリセットできると著者はすすめています。たとえば、ランチのあとに机の上でうつぶせになって、15分間目をつぶるだけでもよいようです。それは、情報処理量が激減するからなのだといいます。
日々、発している疲れのサインを正しくキャッチ。脳の疲労をしっかりとっていきたいものです。
如何でしょうか?鍼灸治療も短い時間で脳の疲れ、自律神経の疲れを回復させていきます。
朝ストレッチで痩せやすく?基礎代謝をアップさせる生活習慣
カテゴリー:院長スケジュール2020年01月15日(水)
年末年始でご馳走を食べすぎたのかダイエットの話をよく耳にします。
そんな時に見つけた記事です。
朝ストレッチで痩せやすく?基礎代謝をアップさせる生活習慣
体温維持や呼吸などで、人が生きていくために最低限必要なエネルギー「基礎代謝量」は、年齢とともに減っていきます。
その原因の一つに、「筋肉量が減ること」が挙げられます。体温をつくり出す働きを担う筋肉は、基礎代謝の中でも多くのエネルギーを必要とするためです。要するに、「筋肉量が少ないと、安静にしていても消費されるエネルギーも少ない」というわけで、それが太りやすくなることにもつながります。
筋肉量が低下し、冷えなどにより血行が悪くなると、代謝がおちて、脂肪を減らすことがますます難しくなります。管理栄養士が、日常でできる代謝UPの方法をご紹介します。
■日常でできる代謝UPの方法
(1)寝起きストレッチ
最近流行している「朝活」。早起きして身体にいいことを始めてみませんか? 朝に身体を動かすと、基礎代謝がUPするといわれています。起きてから、ベッドや布団でできる寝起きストレッチをしてみましょう。
(1)四つん這いの状態から、ゆっくりと重心を足の方にずらしていきます。
(2)腕を伸ばし、背中がしっかり伸びるようにして30秒キープします。
血行がよくなり、日中の活動もはかどるようになるでしょう。
(2)早歩き
20歳以上の人の筋肉は、運動しなければ1年に1%ずつ減少していくとされています。
歩くと、全身で大きな筋肉のある足を使うため、血流がよくなります。その結果、身体のすみずみまで栄養がいき渡り、代謝もよくなります。
早歩きだけではなく、「歩幅」にも注意してみましょう。チョコチョコと歩くのではなく大きく一歩をふみ出すと、より効果的です。
(3)階段を使う
階段を使うと消費エネルギーが上がるイメージがありますが、一段飛ばしで勢いよく階段を上がってはいませんか?
実は、ゆっくりと一段ずつ上がる方が、消費するエネルギーも増えると報告されています。
(4)胸をはり、姿勢を正す
姿勢を正すだけでも代謝UPの効果が期待できます。
正しい姿勢とは、下を向いた時に「自分の足の甲が見える」状態です。ぜひ、確認してみてください。
正しい姿勢で歩くと、重心が前になり移動しやすくなるため、歩くスピードがはやくなります。肺活量も増え、横隔膜がきたえられて基礎代謝量UPにつながります。
ジムに通うのも一つの方法ですが、時間がとれないことも多いですよね。日常の動作を意識するだけでも、筋肉量の減少を緩和することができます。毎日の小さな積み重ねが大切です。意識してとり組んでみてくださいね。
あけましておめでとうございます
カテゴリー:院長スケジュール2020年01月06日(月)

あけましておめでとうございます。 本年もよろしくお願いします。
しんきゅう通信1月号です。
実は冬こそ汗ケアが必要?夏の汗よりニオイがキツイのは冬の汗
カテゴリー:院長スケジュール2019年12月21日(土)
年末年始のお休み所お知らせ
12月29日(日)~1月3日(金)
年始は1月4日(土)から診療します。
暖冬のためか冬なのに汗をかくという話を良くします。そんな時に見つけた記事です。
実は冬こそ汗ケアが必要?夏の汗よりニオイがキツイのは冬の汗
今年は持ち歩ける扇風機「ハンディファン」が流行した猛暑の夏が終わり、ようやく夏のデオドラントケアから解放されホッとしていませんか?実は冬の汗は夏よりもっと臭うのです。冬こそしっかり汗のニオイ対策をしましょう!
そもそも汗が臭うのはナゼ?
汗腺にはエクリン線とアポクリン線の2種類があります。 エクリン線から出る汗は水分に近くサラサラしています。一方、アポクリン線から出る汗はタンパク質やミネラルなどのニオイ成分が含まれ、わきの下や陰部に集中しています。汗をかいたまま放置すると細菌によって分解されますが、分解によってできた物質が独特のニオイを発します。また、わき毛に汗が付着するとニオイが空中に分散されるため、処理をしていない男性は女性に比べて体臭が強くなる傾向があります。
「冬の汗と夏の汗」何が違うの?
夏の間は毎日のように汗をかきます。そのため汗腺はしっかりと機能していますが、冬は汗をかく機会がぐっと減るため汗腺の機能が衰えてしまいます。血液から汗は作られるわけですが、機能が高い(夏の汗腺)は汗を作る際に、ミネラルなどのニオイ成分を血液に再吸収させてから汗として放出するのです。 ところが、(冬の汗線)は機能が衰えているため、この再吸収がうまくいかなくなりニオイ成分が高い汗が出るのです。
夏と冬の汗のかき方の違いでニオイも変わる!?
夏は体温の上昇によって汗がでます。これを「温熱性発汗」と呼び、自然にゆっくりかく汗です。これに対して緊張などで部分的に手のひらや、わきの下にかくストレス性の部分的な汗は「精神性発汗」と呼ばれ、短時間で大量に汗をかくため血液に再吸収させる余裕がなくミネラルやタンパク質成分の高い汗となるのです。 また、「精神性発汗」はアポクリン線の集まるわきの下などから出ることも多いため「精神性発汗」で汗をかくと強いニオイの汗が出てしまうというわけです。
冬のデオドラントケアはどうする?
冬の衣服はコートやセーターなど汗が蒸発しにくい素材が多いので、放置しないよう早めに汗を拭きとりましょう。また、汗腺の機能を高めるとニオイ成分の低い汗が放出されるので、入浴や有酸素運動で普段から汗をかくことも重要です。また、肉は腸内でニオイ成分が生成されるので、野菜が多めの食生活にすると良いでしょう。デオドラントケアとしてミョウバン含まれた制汗剤を使用するのもおススメです。ミョウバンを使用した制汗剤は汗の量を抑え、消臭効果も高く肌を弱酸性に保ち常在菌の繁殖を抑えます。古代ローマ帝国の時代から使用されていた最古の制汗剤というのも納得です。
汗をかく機会減るからこそ、逆にニオイ成分が強くなってしまう冬の汗。臭ってしまったらと不安になると「精神性発汗」につながります。「汗をかいたらすぐにふき取る」「入浴や運動で汗腺を鍛える」「食生活を見直す」などのケアをしましょう。
汗は冬も大切なんです。鍼灸治療は代謝を促進させます。汗をかきにくい人は鍼灸治療で汗をかけるようになると良いですね。
水ゼリーって知ってる?新感覚のダイエットのお供
カテゴリー:院長スケジュール2019年12月13日(金)
ダイエットをしている方に注目を集めている「水ゼリー」を知っていますか? 低糖質・低カロリー・低脂質なので、ダイエット中の間食や水分補給にもぴったりと人気を集めています。
水ゼリーの基礎知識
水ゼリーは、水とゼラチン、寒天、アガーなどから作るゼリーです。誰でも簡単にできますし、「水」で出来ているのでヘルシーで満足感も得られますし、のどが渇いた際の水分補給にもおすすめです。 そのまま食べてもいいですし、カロリーが増えてしまいますが、スイーツとしてより味わいたいのであればきな粉や黒蜜をかけてもより美味しく食べることができます。 また水ゼリーはゼラチン、寒天、アガーそれぞれでカロリーや効果が異なるので、まずはその特徴を理解しておきましょう。
ゼラチンで作る水ゼリー
それではまずはゼラチンで作る水ゼリーについて説明をします。 ゼラチンのカロリーは水ゼリーを1つ作るのに5g使用した場合、約5キロカロリーほどです。ゼラチンはタンパク質が含まれており、さらにコラーゲンも豊富なので肌や髪の毛をきれいにしてくれる効果も期待できます。 触感はくちどけが良く、最もプルプルとしていますが熱に弱いため暑い時期は持ち運ぶことで溶けてしまうこともあります。
寒天で作る水ゼリー
最近、太った太った…という声をよく聞きます。
水を飲んだだけでも太っちゃうという方に読んでいただきたい記事を見つけました。
寒天で作る水ゼリーの特徴は、寒天には食物繊維が豊富に含まれており、水溶性と不溶性のどちらも性質も持っているため、便秘改善にも役立ってくれます。また食物繊維は胃の中で膨らむ効果があるので、食前に食べることで食べすぎを防いでくれる効果も期待できます。 また、寒天は100gで約3キロカロリーしかないのも嬉しいポイントだと言えます。 口の中に入れるとほろっと崩れるような触感ですが、食べすぎは腹痛になってしまう可能性があるので、摂取量は1日6gほどに抑えておきましょう。
アガーで作る水ゼリー
アガーはマメ科の種子や海藻からできていて、ゼラチンと寒天と中間のような触感で、無味無臭で透明度が高いため水ゼリーにも最も使用されています。 また、アガーにも食物繊維が豊富に含まれているので、便秘解消に役立ってくれます。 カロリーは5g当たり16キロカロリーで、ゼラチンと寒天と比べると最もカロリーが高くはなりますが、それでも低カロリーで楽しめる食材だと言えます。
いかがでしょうか? 美容効果を得たい方はゼラチン、ダイエットに力を入れたい方は寒天、より水ゼリーを美味しく食べたい、という方はアガーという使い分けでぜひ作ってみてくださいね。
何かおいしいもの食べたくなりました…。
しんきゅう通信12月号
カテゴリー:院長スケジュール2019年12月05日(木)

しんきゅう通信12月号です。寒くなりましたがまだまだって感じですね。
水分補給をしっかりしてくださいね。