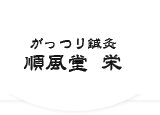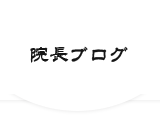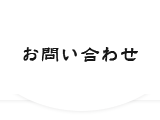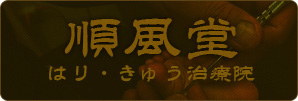こんな時だからこそ「自分ケア」を 心のストレスや不眠を解消する習慣
カテゴリー:院長スケジュール2020年04月09日(木)
緊急事態宣言です。
不要不急の外出を控えてる時です。何かと不自由でストレスが溜まってしまいます。でもこれは大事なことです。みんなが守ればこの事態を早く抜けることができると思っています。ストレスたっぷりの患者さんと話していて見つけて記事です。
春先にこそ「自分ケア」を 心のストレスや不眠を解消する習慣
なんだか気分が晴れない、ちょっとしたことでイライラ……。そんな心の不調で悩む人が多い現代。
誰にでもある“モヤモヤ”と向き合い、うまく付き合っていきましょう。
モヤモヤしたときに
心がすっと軽くなる、簡単なモヤモヤ解消法をいろいろ試して、自分に合った解消法を見つけてください。
気分の落ち込み、イライラ、不眠など、今すぐ病院に行くほどでもないけれど、確実に日常に支障をきたしてくるモヤモヤ状態。
「実は、休みたくても休めない、忙しい世代の女性にこういう不調を抱えている人が多いんです」
「長い間疲れが取れないという人は、栄養ドリンクを飲むよりも、ちょっとした習慣で『脳』から変えていくことが重要。
抗ストレス作用のあるセロトニンを増やす方法や自律神経の整え方など、日常にちょっとした行動を取り入れるだけで心も体も驚くほど楽になり、健康的な美しさへと繫がります。
誰でも気軽に実践できるモヤモヤ解消法で元気を取り戻していただければと思います」
#01 死んだふりをする
どうしようもない疲れやストレスを感じたときは、一度目を閉じ、死んだつもりになってみる。
この世から自分の存在が無くなったつもりで物事を考えると、不思議と今ある悩みが客観視できて他人事として考えられ、冷静に問題に向き合えるようになります。
#02 好きな味のガムを嚙む
精神の安定に深く関わるセロトニンを増やす方法として有効なリズム運動。
ダンスやジョギングが良いとされますが、手っ取り早く取り入れるならガムを嚙むのがおすすめ。
特に、精神を落ち着ける青色のガムを選べば相乗効果でより心の安定が期待できます。
#03 不調の原因は天気かも? と考える
女性は気象により自律神経に影響を受けやすいことを自覚しましょう。天気による不調が普通のことだと分かれば安心できますよね。
「雨の日は頭痛がする」「くもりの日は落ち込みやすい」など自分の体調を把握し、漢方薬や冷え対策などの対処を行うことで楽に。
#04 モヤモヤ解消法を記録する
「お笑い番組を観て笑ったら20点」など「これをしたらモヤモヤが解消した」と感じた行動に点数を付け可視化する。
加点するほどストレスの軽減を意識でき、脳内のモードがプラス方向へ。憂鬱な気分のときこそ、少しでも好きなことに没頭する時間の確保を。
#05 鼻歌を歌いながらスキップする
ストレスを感じたときには、あえて気分の良いときにする行動を。「自分は今とても気分が良い」と脳をだますことで、気持ちが行動についてくるから不思議。
くもりの日など「なんだか家から出たくないな」というときに実施すれば、気持ちが前向きになります。
#06 右向きに寝る
胃は体の右側にカーブするように位置するため、右向きに体を横たえると消化の流れがスムーズに。
自律神経にかかる負担が軽減され、質のいい睡眠に繫がります。
#07 悩みごとを紙に書いて破る
憂鬱な気分が抜けないときは、頭に浮かぶ「嫌なこと」をリスト化してみましょう。書くことで頭が整理され、気分が落ち着きます。
また、意外と自分の悩みの少なさに気づくことも。解決しない大きな悩みがあったら、書いて破って捨てるだけでもすっきりします。
#08 芝生の上で寝転がる
緑色を視覚から取り入れるだけで心が安定します。
また、植物が放つ香りを嗅ぐことで、嗅覚からも心を癒すことができます。観葉植物を育てるのもおすすめです。
#09 誰かをマッサージしてあげる
医療機関でも活用されるタッチ療法。癒しホルモンとよばれるオキシトシンは、親しい人やペットに触れることで分泌されます。
また、アドラー心理学でも他者貢献が幸せの鍵だと言われています。実は、マッサージはされるよりしてあげる方が幸せを感じられるのです。
#10 肩回し&背伸びをする
ストレスと比例して肩や肩甲骨が固まる。そんなときは肩回しや背伸びで肩甲骨周りの緊張をゆるめましょう。
体につられて気持ちもゆるみ、モヤモヤもやわらぎます。深呼吸しながら行えばセロトニンが増加。
簡単にできて効果てきめんなので習慣化しましょう。
#11 チョコレートを食べる
疲れたときについ食べたくなるチョコレート。実は、脳の活性化と精神不調時の症状の改善が期待できると科学的に立証されています。
モヤモヤが続くときはつい過食気味になってしまいますが、問題ありません。重要なのは食べ過ぎてしまっても罪悪感を持たないこと。
「おいしかった」「ストレス発散になった」と幸せを感じることが翌日の過食予防に。
#12 カーテンを開けて寝る
「なんだか最近寝起きがつらい」という方はぜひお試しを。自然と光が部屋に差し込み、すっきり目覚められます。
朝日を15秒以上浴び、太陽の光が目から入ってくることで自律神経が整い、狂いがちな体内時計もリセットされます。
うつ治療でも光療法があるくらい、明るさは一番のモヤモヤ解決法。天気の悪い日は蛍光灯でもいいので、とにかく明るくしましょう。
#13 映画を観て泣く
モヤモヤする気うつ、気滞状態は、涙で気の巡りを良くすれば驚くほどすっきりします。
涙1滴で、ストレス解消効果が1週間も続くといわれるほど涙効果は絶大。
悔し涙でも、どんな涙でもいいんです。週に一度、映画などを観て意識的に泣くのもいいでしょう。
#14 ジャスミン緑茶を飲む
強いストレスを感じたら、ジャスミン茶と緑茶の茶葉を1対1の割合で混ぜて淹れる「ジャスミン緑茶」で一息を。
ジャスミンの香りは自律神経を整えるほか、ストレスによる胃痛・腹痛、うつ気分の改善にも効果あり。
ビタミンC・Eが豊富で美容効果も期待できます。そこに気分を安定させる緑茶のうまみ成分「テアニン」を加えれば、より気持ちがやわらぎます。
#15 とにかく体を温める
人間は寒いと気持ちが弱ります。
また、冷えは万病のもとといわれるように、冷えることで免疫力が低下し、風邪をひきやすくなり、自律神経が乱れ、慢性的な疲労や頭痛が起こるなどの症状が現れます。
カイロを貼る、温かい飲み物を飲むなど冷え対策を万全に。
#16 きれいな姿勢をキープする
姿勢を支えるためには、背中や腰、お尻などの抗重力筋が活躍しますが、この筋肉を使うことで幸せホルモンのセロトニンが分泌されるといわれます。
見た目が美しくなり、さらにストレスを感じにくい状態になれるなんて、女性にとって一石二鳥ではないでしょうか。
#17 ジンギスカンを食べに行く
疲れたときのご褒美ごはんは焼肉よりもラム肉でヘルシーに。ラムは肉の中でも栄養価が高く、ビタミン、ミネラルを多く含む食品。
疲労回復やストレス解消効果のあるビタミンB1も多く、疲れない体作りに最適。さらに脂肪燃焼を促進するL-カルニチンも豊富。
#18 左手で歯磨きをする
イメージなど非言語系の情報を処理する右脳。意識的に左手を使うことで右脳が活性化し、新しいアイデアが浮かびやすく、問題への打開策が見つかる可能性が高まります。
文字を書いたり、箸を使うのは難易度が高いですが、歯磨きならば取り入れやすいでしょう。
#19 「青」を取り入れる
色彩心理学でも色は思考や心理、行動に影響を及ぼすと証明されています。なかでも青色は、セロトニンを分泌させ集中力を高める効果あり。
緊張する場面で目に付く場所に青を取り入れると良いでしょう。食欲を抑える効果もあるため、ダイエット中の人にも。
#20 腸内環境を整える
精神的な安定を求めるならば、お腹を整えましょう。なぜなら幸せホルモン・セロトニンの素はお腹の中に90%あるといわれているのです。
納豆などの発酵食品で腸内環境を良くすると精神も好転します。腸内環境を整えることを日頃から心がければ、不調の予防に。
#21 宇宙の本を読む
ネガティブ沼から抜け出したいときには、宇宙について思いを馳せてみてください。
「宇宙の果ては?」などと考え出すと、現実の悩みがちっぽけに感じます。
#22 モーツァルトを聴く
気持ちの切り替えや癒しに効果を発揮する音楽。
特にモーツァルトの曲は「心拍数を安定させる」「イライラを落ち着かせる」「集中力を上げる」「作業のスピードを上げる」「ミスを減らす」など、人の脳や心理に働きかけることが科学的にも証明されています。
いろいろな方法でストレス解消です。
みんなで頑張ってみんなで乗り越えていきましょう。