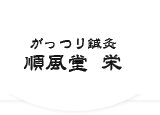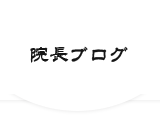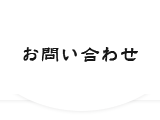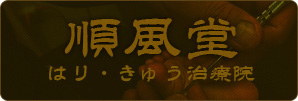あなたの体質に合ったみそ汁は? 体調管理に役立つ「おうち薬膳」を楽しもう
カテゴリー:院長スケジュール2021年02月08日(月)
簡単に健康を維持、増進したい患者さんとの会話で見つけた記事です。
あなたの体質に合ったみそ汁は? 体調管理に役立つ「おうち薬膳」を楽しもう
外出自粛の影響もあり、家で食事をする機会が多い今。普段とは違う角度から「食」について考えてみませんか。テーマはみそ汁。健康状態を知るバロメーターとして、薬膳の観点から6つの体質の特徴とそれぞれの体質に合ったみそ汁の具材について解説します。もちろん体質など関係なく、見て気になったみそ汁でも構いません。薬膳の知恵が詰まった温かい1杯を作って食べて、心豊かに過ごしましょう。
◇ ◇ ◇
身近な食材で簡単に 朝ごはんにみそ汁で元気な1日のスタートに
一見とっつきにくいと思われる薬膳ですが、昔からの知恵として無意識に生活に取り入れられていることが多く、とてもシンプル。「自分の身体の不調や変化に気付き、それらを補う働きの食材を選んで食べる」という仕組みを知れば、身近な食材で簡単に家庭料理を作ることができます。今回は、“日本のソウルフード”と呼ばれる和食の定番・みそ汁を薬膳の視点から考えてみました。みそ汁(スープ、汁物)の良さは、食材の栄養素を逃さず摂取できること。特に、朝ごはんに食べる温かいみそ汁は、睡眠中に冷えた身体を温め、1日を元気にスタートさせてくれるでしょう。
薬膳の知恵から6つのみそ汁を紹介します。前回紹介した体質チェックから、今の自分の心と身体の傾向のタイプを知り、みそ汁一覧から選びます。もちろん、チェックせずに、読んで気になったみそ汁を作っていただいても構いません。薬膳は、食事の面から健康を考える食養生と、生活習慣を見直す生活養生を平行して行うことでより効果を実感できます。暮らしのヒントの1つとして取り入れ、コツコツと健康の土台を作り上げましょう。
薬膳の知恵 6つの体質別で おすすめのみそ汁とは
○Aタイプ 気が不足している「気虚(ききょ)」
エネルギーが消耗してぐったり。身体が冷えやすく、風邪も引きやすい。
<おすすめの具材>
シイタケ:気を補い、免疫力アップ
山芋:気を補い、滋養強壮
卵:虚弱体質の改善。身体を潤す
【ポイント】
シイタケは元気を補い、身体を丈夫にするパワフルな食材です。ただし、デリケートなので、素材の働きを逃がさないように水で洗わず、弱火でゆっくりと長めに火を通すのがコツ。山芋は地味な存在ながら、「山薬」という名前の漢方薬としても使われる優秀な薬膳食材です。
○Bタイプ 気が滞っている「気滞(きたい)」
身体全体をめぐるエネルギーが停滞してストレスを感じやすい。集中力もない。
<おすすめの具材>
春菊:気のめぐりを良くする。眠りの質の改善
大根:消化を促す。気のめぐりを良くする
ユズ:気のめぐりを良くする。胃の不快感にも
【ポイント】
気をめぐらせるためには、香りの良い食材が効果的です。香草(春菊、三つ葉、セロリ)や柑橘系との相性は抜群。中でも春菊は「安神作用」という、精神を安定させる働きもあります。香りの良い食材はアロマ効果を生かし、さっと軽く加熱する程度で食べましょう。
みそ汁の良さは、食材の栄養素を逃さず摂取できること
○Cタイプ 血が不足している「血虚(けっきょ)」
心と身体に栄養と潤いを与える血が足りない。貧血の傾向や肌の乾燥なども。
<おすすめの具材>
ニンジン:血を補い、胃腸の働きを整える
シメジ:気と血を補い、便通を良くする
小松菜:身体を潤し、ほてりやのぼせの解消も
【ポイント】
血虚は消化吸収の力が低下していて、血を作るエネルギーが足りない状態。こういうタイプはお肉による補血よりも、胃腸を整えながら血を補うニンジンがおすすめです。また、血不足(=潤い不足)の乾いた肌に潤いを作る小松菜は、カルシウムやβ-カロテンも豊富です。
○Dタイプ 血が滞っている「お血(けつ)」
血の流れが滞り、栄養がめぐらない状態。肩こりや肌荒れ、生理痛も起こりやすい。
<おすすめの具材>
ホウレン草:血を補う、夜盲症にも
ジャガイモ:お腹を元気にする
玉ネギ:血と気をめぐらせる
【ポイント】
川の水が少なければ淀むように、体内に流れる血液の量が不足すれば、血も滞ります。現代人の血が滞りがちな原因1つに血の不足があると言われているので、摂取した飲食物からしっかり栄養(血)を作れるように、お腹の働きを元気にするジャガイモを組み合わせました。
○Eタイプ 潤いが不足している「陰虚(いんきょ)」
身体の潤いが足りない。熱を冷ます力がないので、ほてりやのぼせ、便秘傾向にも。
<おすすめの具材>
豆腐:身体を潤し、余計な熱を冷ます
豚肉:身体を潤し、血と気を補う
白ゴマ:身体を潤し、加齢によるトラブルにも良い
【ポイント】
潤い不足によるほてりや熱感、イライラには、潤いを補う食材のセットをどうぞ。陰虚タイプは、夕方以降ほてりや熱感が増すので、夕食時に食べるのが良いでしょう。豚肉の脂肪分は腸の潤滑油になり、腸粘膜の乾燥から来る便秘の解消にも効果的です。
○Fタイプ 水が滞ってる「痰湿(たんしつ)」
水分代謝ができず、体内に過剰な水分が溜まる。身体が重く、胃腸の働きも今いち。
<おすすめの具材>
昆布だし:身体のしこりをほぐし、むくみを解消する
アサリ:血行を良くして水分代謝を促す
大根:消化を促し、気のめぐりを良くする
【ポイント】
薬膳の視点では、アサリの身ではなく殻に薬効成分があると考えます。アサリを昆布だしでじっくりと煮込んで、殻から出るエキスを存分に活用するのがおすすめの食べ方。アサリは身体を冷やす傾向がある食材なので、冷え性の人は身体を温めるネギを加えましょう。
Aタイプ 気が不足している「気虚(ききょ)」
Bタイプ 気が滞っている「気滞(きたい)」
Cタイプ 血が不足している「血虚(けっきょ)」
Dタイプ 血が滞っている「お血(けつ)」
Eタイプ 潤いが不足している「陰虚(いんきょ)」
Fタイプ 水が滞ってる「痰湿(たんしつ)」
いかがでしょうか?お味噌汁は毎日、飲まれている方が多いと思います。
ひと工夫で健康に役立つなら試す価値はアリではないでしょうか?