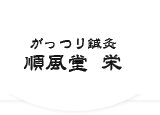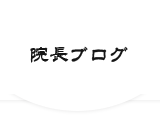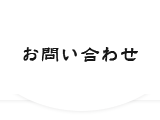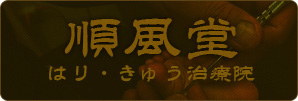低気圧で頭痛やめまいを感じる人へ! 「自律神経の乱れを整える」簡単な方法
むち打ちの人は首が天気予報とよく言いました。
最近は体調がすぐれないと雨が近いという人が増えていると思います。そんな患者さんとの会話で見つけて記事です。
低気圧で頭痛やめまいを感じる人へ! 「自律神経の乱れを整える」簡単な方法
頭が何となく痛くなると「明日は雨かも」と思う人は一定数いるでしょう。低気圧が近づくと不調になりやすい人は、血液やリンパの流れが悪かったり、水分代謝が良くなかったり、自律神経が乱れていたりする場合が多いそう。
低気圧が近づくと不調になっていませんか?
春らしい日が続いたと思ったら、週末には低気圧が発達し、冬型の気圧配置となる予想です。また、真冬のような寒さに逆戻りし、雪や雨が降る地域も出てくることだと思います。今月はずっとこんな感じの気候の変化を繰り返しすぎていくと思いますが、そうすると困るのが低気圧で毎回不調を感じているタイプの人たちではないでしょうか。
低気圧が訪れると、頭痛やだるさ、めまい、むくみ、耳鳴り、憂うつな気分になるなどの不快症状を感じやすくなることがあります。春というと、生活環境の変わり目でもあり、明るい気分で前のステージから次へと移り替わり、元気に新しい環境へと適応していきたいところですよね。そこで、季節の変わり目の低気圧による不調を軽減する食薬習慣を紹介します。
低気圧による不調を軽減する食薬習慣
ようやく暖かくなったのに週末にはまたもや低気圧が徐々に発達することで、冬型の気圧配置となり荒れ模様の空へと変化してしまうことでしょう。ただ、今月末には桜が開花する地域もあり、あと一歩で春へたどり着きそうな心弾むときでもあります。
そんな今の時期を元気に過ごすためには、低気圧に動じにくい体づくりが必要となると思います。漢方では、気圧の変化に体調が乱されやすい人は、肩から首、耳周辺までのリンパや血液の巡りが悪かったり、水分代謝の悪かったりする傾向があるとされています。
これを『気滞血瘀』や『痰湿』などと呼び、三半規管が弱かったり、自律神経が乱れやすいと考えます。そこで、『気滞』・『瘀血』・『痰湿』の改善に役立つ食薬がおすすめです。
食べるとよい食材・メニューは、【アボカドとグレープフルーツのサラダ】です。
作り方は、アボカドをスライスして、グレープフルーツは一口大にカットし、皿に盛り付けます。塩少々とオリーブオイルとお酢を全体にかけたら完成。
【アボカド】
ギネスに認定されるほど栄養が豊富なアボカドには、血流を促し『瘀血』の改善に役立つビタミンEや代謝を促すビタミンB群、『痰湿』の除去に役立つカリウムをはじめとしたミネラルや食物繊維などが豊富に含まれています。
【グレープフルーツ】
食欲を抑えたり、リラックス作用のある香り成分が『気滞』の改善に役立ちます。代謝を促すクエン酸や余分な水分の排泄に役立つカリウムなども含まれます。また、薄皮ごと使うことで食物繊維もとることができるため急な血糖値の上昇を抑えたり、便通を促すことができ『痰湿』の除去に働きます。
水分代謝が悪かったり、自律神経が乱れがちな人は、気圧の変化が大きいとき小さな不調がでてきやすくなります。低気圧の予報を見たら一度今回紹介したサラダを食べてみたり、いつもより少し早く寝るようにしてみたり、足のマッサージをしたり、ストレッチをしたり、巡りを改善するようなことを試してみて下さい。その中で、自分にとってどんな方法がベストなのかを低気圧のたびに検証し、少しずつ自分の体質を変えていけるのが理想です。
食事であの嫌な感じを改善できるのはうれしいですよね。
おいしいもの食べて体調も万全は理想です。