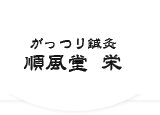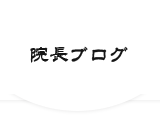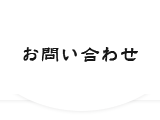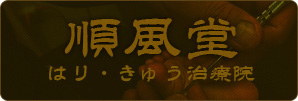「血圧の薬」を飲み忘れるとどうなる?薬の種類や副作用についても医師が徹底解説!
血圧の不安定な状態な患者さんが多いです。そんな患者さんとの会話で見つけた記事です。
「血圧の薬」を飲み忘れるとどうなる?薬の種類や副作用についても医師が徹底解説!
高血圧の治療に欠かせない「血圧の薬」。しかし、うっかり飲み忘れてしまった場合、体にはどのような影響があるのでしょうか。
また、薬には種類ごとの特徴や副作用もあり、正しい理解が欠かせません。本記事では、血圧の薬の種類や副作用、服用する際の注意点などを先生に解説していただきました。
血圧とは?
血圧とは、心臓から血液が送り出された時に血液が血管の壁を押す力のことです。まずは血圧の基礎について、簡単に解説します。
・血圧の数値で体の何がわかる?
血圧の数値を調べると、心臓と血管の状態が分かります。たとえば、高血圧が続いている場合は、動脈硬化や腎臓への負担、心筋梗塞・脳卒中などのリスクが高まっている可能性があります。つまり、血圧の数値は全身の血流の状態や臓器への負担を知る手掛かりとなるのです。
・血圧の測定方法
血圧は日常的に変動しており、身体の正確な状態を知るには毎日同じ状況で測る家庭での血圧の把握が欠かせません。毎日朝晩に、静かで落ち着いた状態で血圧を測定しましょう。血圧の状態によっては、夕食前や調子の悪いときなどのタイミングで追加の計測が必要な場合もあります。
血圧の薬の種類
血圧の薬は、作用の仕組みが異なるさまざまな種類があります。ここでは、代表的な薬を紹介します。
[カルシウム拮抗薬]
カルシウム拮抗薬は、血管の壁や心臓の細胞にある「カルシウムチャネル」という部分に作用して血管を広げ、血圧を下げる薬です。血圧を安定して確実に下げるだけでなく、使えない病気が少ないことから最初の薬としてもよく選ばれます。代表的な薬は、アムロジピン、ニフェジピンなどです。また、カルシウム拮抗薬を服用している方がグレープフルーツジュースと飲むと、薬の効果が強く出る場合があります。ジュースの効果は3~4日続くといわれているため、カルシウム拮抗薬を服用している方は、グレープフルーツジュースは避けましょう。
[ACE阻害薬・ARB]
ACE阻害薬(アンジオテンシン変換酵素阻害薬)とARB(アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬)は、どちらも血管を収縮させて血圧を上げる物質「アンギオテンシンⅡ」の働きを抑えて血圧を下げる薬です。それぞれの薬の効く仕組みは、以下のとおりです。
ACE阻害薬:アンギオテンシン変換酵素(ACE)という酵素の働きを妨げて、アンギオテンシンⅡが作られるのを防ぐ
ARB:アンギオテンシンⅡが結合する場所(受容体)をブロックして働きを妨げる
どちらも、血圧を下げる効果に加えて、心臓や腎臓を保護する作用も期待できます。代表的なACE阻害薬はエナラプリル、リシノプリルなど、ARBはカンデサルタン、オルメサルタンなどです。
[利尿薬]
身体に水分が溜まっていると、心臓が動くのに多くの力が必要になり血圧が上昇しやすくなります。利尿薬は、腎臓に働きかけて身体の余計なナトリウムや水分を尿として排泄させ、血液量を減らして血圧を下げる薬です。代表的な薬は、トリクロルメチアジド、ヒドロクロロチアシドなどです。また、作用する方法はやや異なりますが、スピロノラクトン・エプレレノンという利尿薬と似た仕組みを持つ血圧の薬もあります。
[β遮断薬]
β遮断薬は、血管ではなく心臓にあるβ受容体という部位に働きかけて心臓の動きをゆっくりにし、心臓が送り出す血液量を減らして血圧を下げる薬です。狭心症や心不全、頻脈など、心臓や脈の異常がある方に多く処方されます。気管支喘息のある方には適さない薬もあるため、必ず医師へ伝えてください。代表的な薬は、ビソプロロール、プロプラノロール、アテノロールなどです。
血圧の薬の副作用
血圧の薬は、血圧を下げる効果の裏返しとして、もしくは薬に特有の特徴として副作用が起こる場合があります。代表的な副作用と、起こりやすい薬を知っておきましょう。
[ふらつき・めまいが出る]
薬によって急激に血圧が下がると、脳に十分な血液が行き渡らなくなり、ふらつきやめまいが出ることがあります。どの血圧の薬でも起こる可能性があり、薬の飲み始めや、量を増やした際に起こりやすいです。いきなり立ち上がったり急に動いたりすると出やすくなるため、立ち上がる際は何かにつかまり、ゆっくりとした動作を心がけましょう。また、車の運転や危険な作業は避けてください。症状が続く場合は、薬を処方した内科・循環器科へ早めに相談しましょう。血圧の状態によっては、薬の種類や量を再調整する場合もあります。
[むくみが出る]
ACE阻害薬・ARBを飲んでいる方に、突然のむくみが起きた場合は「血管浮腫」という副作用の可能性があります。かゆみや赤みはなく、通常のむくみと違い、指で押しても痕が残らないのが特徴です。強いむくみが喉や口の粘膜にあらわれると、呼吸が苦しくなる可能性があるため、早めの受診をおすすめします。また、むくみはカルシウム拮抗薬により血管が拡張することでも起こります。むくみが出ている場合は、心臓や腎臓の機能が低下している可能性があるため、続く場合はかかりつけの内科・循環器科を一度受診しておくとよいでしょう。
[乾いた咳が出る]
ACE阻害薬を飲み始めてしばらくすると、痰の絡まない乾いた咳(空咳)が出る場合があります。これは、ACE阻害薬の作用によって増えた「ブラジキニン」という物質が気道を刺激するために起こると考えられています。薬を中止すれば治まる副作用ですが、自己判断での中止は血圧コントロールが不安定になるため、危険です。咳がつらい場合は早めにかかりつけの内科・循環器科を受診して相談しましょう。
[手足やくちびるなどにしびれが出る]
一部の利尿薬では、服用によって体内の「カリウム」というミネラルのバランスが崩れて、しびれや脱力感などが出る場合があります。利尿薬の種類によって、カリウムが多くなりやすいか少なくなりやすいかは異なります。
高カリウム血症:筋力の低下、しびれ、脈の乱れ
低カリウム血症:手足のだるさ、こわばり、脈の乱れ、筋肉痛
放置すると不整脈により致命的となる可能性があるため、かかりつけの内科・循環器科を速やかに受診しましょう。
[歯肉の肥厚]
カルシウム拮抗薬の中には歯肉の肥厚をきたすことがあります。カルシウム拮抗薬は使用頻度が多いため、歯肉の肥厚は頻度が多い副作用の一つです。一般的には原因となるカルシウム拮抗薬を中止して、他の薬剤へ変更することで改善します。歯科で歯肉の腫れ、肥厚を指摘された場合には、主治医へ相談をしてみましょう。
医師が血圧の薬を処方する人の特徴
血圧が高くても、すぐに薬が開始されるとは限りません。血圧がそれほど高くない場合には、生活習慣の改善をまず行い、それでも血圧が十分に下がらない場合や、以下のような特徴を持つ人には、薬の処方が検討されます。
[生活習慣病がある]
糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病を合併している方は、血管が傷みやすかったり動脈硬化のリスクが高かったりします。そのため、特に複数の生活習慣病がある場合は早めに薬の処方を開始します。
[心臓や脳などに持病がある]
以下のような心臓、脳、血管に持病や過去の病歴がある方は、病状の悪化の予防、再発予防のためにしっかりとした血圧コントロールが必要です。
・過去に心筋梗塞や狭心症の発作を起こしている
・大動脈解離大動脈瘤などの血管の病気がある
・心不全が持病にある
・過去に脳卒中(脳梗塞・脳出血)を起こしている、脳動脈瘤がある
・腎臓病がある
腎臓は細い血管が集まっているため、高血圧によってダメージを受けやすい臓器です。また、逆に腎臓病が高血圧を引き起こすこともあります。高血圧を放置すると、腎機能が低下し血圧がさらに上がる悪循環におちいるケースが珍しくありません。また、蛋白尿を伴う慢性腎臓病では、蛋白尿を減少させ、腎臓を保護する目的で血圧が低くともACE阻害剤やARBといった降圧剤を使用することもあります。
[たばこを吸う]
喫煙は血管を収縮させ、動脈硬化を促進する危険因子です。たばこを吸う方は吸わない方よりも心臓や脳の病気になりやすいため、適切な血圧を保つことが非常に大切です。また、たばこに含まれるニコチンや一酸化炭素自体も血圧を上昇させ、高血圧を悪化させる可能性があります。禁煙が理想的ですが、まずは減煙からでも始めてみましょう。
血圧の薬を服用できない人の特徴
血圧の薬は多くの人にとって有効ですが、服用できなかったり、特に慎重な投与が必要になったりする場合もあります。薬によって異なりますが、血圧の薬を服用できない人の例をいくつか紹介します。
[飲み合わせの悪い薬を服用している]
一部の血圧の薬は効果が強くなりすぎたり弱くなったりする可能性があるため、いっしょに飲めない薬があります。たとえば、以下のような薬です。
一部のカルシウム拮抗薬:抗真菌薬や抗ウイルス薬の一部
一部の利尿薬:一部の免疫抑制剤
また、いっしょに飲むことはできるものの、薬の量や種類を慎重に検討する必要がある薬も少なくありません。飲んでいる薬がある方は、必ず医師・薬剤師へ伝えるようにしてください。
[その薬の成分にアレルギーがある]
過去に特定の降圧薬で発疹、かゆみ、アナフィラキシーショックなどのアレルギー反応を起こしたことがある場合、同じ系統の薬も避ける必要があります。薬のアレルギーがある場合は、必ず受診時に伝えるようにしてください。
[腎臓・肝臓の機能が大きく落ちている]
多くの薬は、腎臓や肝臓で代謝・排泄されます。そのため、腎臓や肝臓の機能が大きく弱っていると、薬の代謝ができずに、効果が強く出すぎたり副作用が出やすくなったりする可能性があります。臓器の状態によって適切な薬の種類や量が異なるため、健康診断で異常を指摘されたことのある方や他の病院で治療を受けている方は必ず医師へ伝えてください。
血圧の薬を飲み忘れたらどうなる?
血圧の薬を飲み忘れると、薬の効果が切れて血圧が上がる可能性が高いと考えられます。一度の飲み忘れで重篤な症状が出るケースはまれですが、飲み忘れが多くて血圧コントロールが悪い状態が続くと、脳梗塞や脳出血、心不全などのリスクが上がる可能性があります。早い段階で飲み忘れに気づいた場合は、1回分を服用するのが基本です。決して次に飲むタイミングで2回分を飲んではいけません。薬の種類や服用回数によって詳細は異なるため、飲み忘れた際の対処法を医師・薬剤師に確認しておくとよいでしょう。
血圧の薬を服用する際の注意点
血圧の薬を安全かつ効果的に服用するために覚えておきたい注意点を解説します。
[指示された飲み方を守る]
血圧の薬は、現在の血圧の状況や持病の有無などから、一人ひとりにあわせたものが処方されています。自己判断で薬を調節してしまうと、血圧の変動が大きくなったり、十分な効果が得られなかったりする可能性があるため、必ず医師が指示した飲み方を守りましょう。副作用を疑う症状や、体調の変化がある場合は早めに受診して指示を仰ぐようにしてください。
[他の病院にかかる時は飲んでいる薬のことを伝える]
他の病気で別の医療機関を受診する際や、歯科治療を受ける際、薬局で市販薬を購入する際などは、必ず血圧の薬を服用していることを伝えてください。「お薬手帳」を活用すると、正確な情報を漏れなく伝えられます。
[気になる症状が出たら早めに医師・薬剤師へ相談する]
服用後に体調の変化や普段と違う症状が現れた場合は、自己判断で服用を中止せずに、速やかに医師・薬剤師に相談してください。副作用の程度や種類によっては、薬の変更や量の調整が必要になる場合があります。
編集部
まとめ
血圧の薬には、カルシウム拮抗薬、ACE阻害薬、ARB、β遮断薬、利尿薬などのさまざまな種類があります。それぞれの薬は異なる方法で血圧を下げるため、医師の指示する飲み方を守って正しく服用することが非常に大切です。高血圧は治療が長期にわたり、自覚症状がないケースも多いため、自己判断で薬を中止して体調が悪化するケースが珍しくありません。将来の脳梗塞、脳出血、心筋梗塞などのリスクを軽減するために、ぜひ自分が処方された血圧の薬について知り、正しく飲むことを心がけてください。
薬は大事です。 用法容量はしっかり守りましょう。